「少し話しただけなのに、なんでこんなに疲れるんだろう…」 そんなふうに思ったことはありませんか?
ASD(自閉スペクトラム症)傾向と境界知能、そしてHSP(繊細さん)の気質を持っていて、昔から人と話すことに苦手意識がある人もたくさんいます。私もこの3つの特性を持っていることから雑談になると、頭が真っ白になったり、会話が終わったあとぐったりしてしまうことが多いです。
この記事では、同じように「会話で疲れてしまう」人に向けて、その理由と私なりの対策をお伝えします。
情報処理が追いつかない
ASDや境界知能の傾向があると、相手の話の意図を瞬時に読み取ったり、その場にふさわしい返答を出すことに時間がかかるため、その場での会話が苦手と感じやすくなります。
\情報処理が追い付かない理由/
・ASDは新しい情報を処理するのが苦手です。
・境界知能人は耳で聞いた情報を脳で処理するのに時間がかかります。
という理由から雑談はとくに予測が難しく、話題がコロコロ変わるため、脳の中で処理が追いつかず、会話が終わったあと、どっと疲れてしまうのです。
【対策】
- 「うん、そうなんだ」「それってどういうこと?」など、シンプルな相槌を用意しておく
- 会話の内容を全部理解しようとせず、「この場をやりすごす」ことを目的にする
- 気を使って話過ぎてしまう人は、「聞く」に徹する
「相手の気持ち」と「自分のいう言葉」を考えすぎてしまう
HSP気質が強い人は、相手の表情や声のトーンに敏感です。
「今の言い方、失礼だったかな…」 「ちょっと相手が不機嫌かも?」 など、常に相手の気分を気にして、会話中も気を張ってしまいます。また自分の発言する言葉にも正確性を求めるので、責任感も人一倍強く、気を張り続けてしまいます。
【対策】
- 「相手の気分は相手の責任」と割り切る(自分のせいと考えすぎない)
- 疲れたときは早めに会話を切り上げるクセをつける
- 相手は自分が思っているほど、気にしていないことを理解する
HSPは、相手の着ているもの、新しく買ったもの、髪型を変えたなどの外見的なちょっとした違いにもすぐに気が付くこと以外に、その日の相手の声のトーン、ちょっとした表情、視線、息遣いなど、一般の人が気づかない細部までキャッチしてしまうので、過敏に反応するのを意識して気にしないようにすることも必要です。
自分の気持ちを言語化するのが難しい
ASDや境界知能の傾向があると、自分の気持ちを瞬間的にうまく言葉にするのが難しい傾向があり、あとから「ああ、あの時、私はこういいたかったんだ」「こういえば良かった」など反省会をすることも多いです。
「何をどう話したらいいかわからない」 「自分でも自分の気持ちがよくわからない」 という感覚があると、会話自体がストレスになることもあります。
【対策】
- よくある話題に対する「自分のテンプレ回答」をあらかじめ考えておく
- 無理に自分のことを話そうとせず、聞き役に徹するのもOK

当事者の私は、人と会ってモヤモヤしている気持ちを持った時に、このモヤモヤがなんなのかを自分で把握するのに、一晩かかることが多いです。
「会話が苦手」は悪いことじゃない
「人とうまく話せない自分はおかしいのかな」 「もっと社交的にならなきゃ」 と思ってしまうこともありますが、会話が苦手なことは、決して欠点ではありません。
むしろ、深く物事を考える力や、空気を敏感に察知する力があるからこそ、疲れてしまうのです。
誰とでも無理に話そうとせず、「安心できる人」との会話を大切にすることが、自分を守る一歩になります。
HSPが自然が好きな理由
HSP気質の人は自然や動物など感覚で感じられるものと触れると、敏感に反応する能力があるため、一般の人よりもきれいな景色を見たときの感動は2~3倍です。その為、自然を感じられる場所に行くと感動して涙を流したり、嬉しくなったりします。

映画鑑賞についても感受性が強いため、途中からみても物語の中に簡単に入り込み、涙する能力もあります。
一般の人だと、途中から映画を見ると意味がつかめない。という結果になる人が多いです。
まとめ
- 雑談や会話で疲れるのは、脳の処理が追いつかない・気を使いすぎる・自分の気持ちを言語化しづらいから
- あらかじめ相槌やテンプレを用意したり、無理に話そうとしないことで疲労を軽減できる
- 「話すのが苦手」は決して欠点ではない。自分に合った会話スタイルを大切にしよう
疲れやすい自分を責めず、自分に優しい選択をしていきましょう。
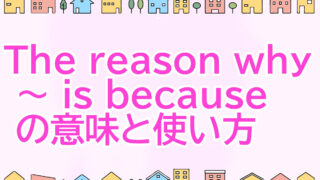
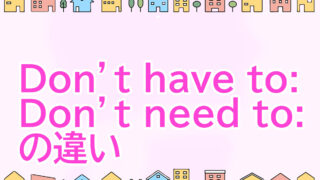




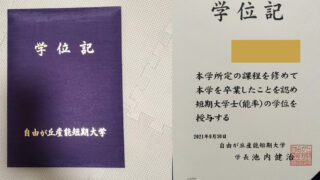


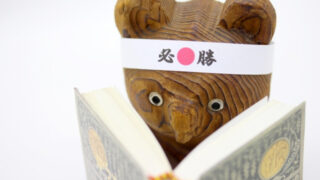











コメント