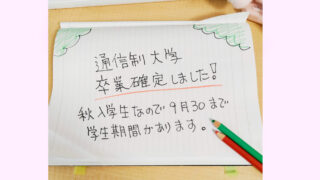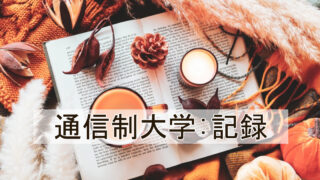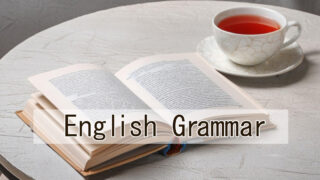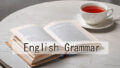「人の名前が覚えられない…」
「あとで質問しようと思っても、内容そのものを忘れちゃう…」
そんなモヤモヤを長年抱えてきた私ですが、知能検査を受けてみて、その原因が ワーキングメモリ(頭の中のメモ帳) の小ささにあると知りました。
私は 境界知能・ASD傾向・HSP という3つの特性を持っています。
そのため日常の中で「できないこと」「難しいこと」にたくさんぶつかってきました。
この記事では、同じように悩んでいる方が「自分を責めすぎないように」…そんな思いを込めて、
ワーキングメモリが低いとどんなことが難しいのか、通信制大学や英語学習で実際に感じた壁 を体験談としてまとめます。
※これは医療・診断ではなく、あくまで個人の体験談です。気になる方は医療機関や心理検査も検討してください。
ワーキングメモリとは?「頭の中のメモ帳」
脳内のワーキングメモリはどんなものかというと「頭の中のメモ帳の大きさ」みたいなものです。
- 会話や作業の一時的な記憶置き場
- メモ帳の容量が小さいと同時にいろいろやったり、必要なことだけを覚えるのが難しくなります
境界知能の人は通常IQの100と比べると85以下のことが多く「頭のメモ帳も小さい」。そのため、一部のことが通常の人と比べて出来ないことがあります。
けど、見た目は普通に見えるので、周りからは気づかれない、または理解されることが少ないため、本人は辛い思いをする場面が人生の中で何度もあります。
境界知能の私が感じる「できないこと・難しいこと」
ワーキングメモリが70程度の私が日常で感じている「難しいこと」です。
1)複雑な会話についていけない
複数人での会話は言葉が飛び交うため、それらの言葉を脳内で処理して、臨機応変に返答をすることが難しいです。会話が進行してる中で、頭のメモ帳が小さいため必要な情報が上書きされ、核心が抜け落ちる、返答がちぐはぐになることがよくあります。
2)同時進行の動作が出来ない
歩きながらスマホを触る、歩きながら水を飲む・食べる、食事しながら会話を楽しむ、会話しながら支度をする、電話しながらメモを取る、授業を聞きながらメモを取る、走りながらボールを取る・投げるなど、一般の人が当たり前にしていることが出来ません。
3)段取り・マルチタスクが崩れる
事務職の仕事にありがちな、「まずA、その間にBも進めて、終わったらC」…といった同時進行が難しいです。1つのことをするのに時間がかかるのと同時進行が苦手の為、ストレスがたまり、1つも処理できなくなる可能性が高いです。
そのため、私は多くの女性が仕事で事務職についていますが、私の中では一番苦手な職種です。
4)勉強・読解のハードル
授業などで先生にあてられて、1段落を読むことになったとします。一応スラスラ読めるのですが、内容が全く頭で処理されていません。そのため、「主人公は何を思っていましたか?」と質問されても答えられず、今読んだところを3回ほど急いで読み返して、慌てて答えると言う行動を取る事が多いです。つまり、声に出して読めても、同時に意味理解が追い付いていないのです。
5)暗算・計算が苦手
数学よりも算数、つまり簡単な繰り上がる計算が出来ないことが多いです。時間をかければできるけど瞬間的な回答が出来ないことが多いです。
多くの一般の人は8+7を計算するときに繰り上がり、繰り下がりの数字を頭のメモ帳に一時的に置いて足して計算していますが、メモリが小さいので頭に置いた数字が消えてしまうことが多いんです。

ここまで読んで、共感した人いましたか?それとも「そうなんだ、大変なんだね」と優しく思ってくれましたか?

境界知能・ASD・HSPの私の強み
ここまで読むと「できないこと」ばかりに見えるかもしれませんが、私は 通信制大学を卒業し、資格試験にも合格 しています。
ショパンやベートーベンの曲をピアノで弾けるし、水泳で500m泳ぎ続けることもできます。
その理由は、ASD特性による「コツコツ続けられる力」が大きいと思っています。
つまり 努力が実を結ぶ形で発揮されやすい のです。

ASD,HSP,境界知能のトリプルを持っていることが強みになってます!
また人の能力を図る方法としてEQも存在します。
EQとは?
人の才能はIQだけでは測れないものだと、専門医が言っています。
EQ(Emotional Intelligence Quotient)っていうのは、「心の知能指数」とも呼ばれていて、自分や他人の感情を理解し、うまく扱う力のことなんです。
たとえば、怒りや不安を感じたときに冷静に対応できたり、相手の気持ちに寄り添ったりする力もEQの一部なんです。
私はおそらく感受性が強いHSPのため、検査はしていませんがEQが高いと思います。
境界知能でHSPでASDのトリプル特性を持っているけど、それぞれがうまく調和してる気がしています。みんなはどうですか?
まとめ
ワーキングメモリが小さいと、確かにできないことは多いです。
でも、それを理解して工夫すれば「自分なりのやり方」で道を切り拓くことは可能です。
私は通信制大学を卒業できたし、英語学習も少しずつ積み上げています。
☑続きの記事↓ワーキングメモリ鍛え方は70→75!私が成功した対策!