発達障害や境界知能を持っていても、「勉強ができる人」と「なかなか結果が出ない人」がいます。
同じような特性を持っていても、その差はどこから生まれるのでしょうか?
この記事では、実際に私自身の体験をまじえながら、
「勉強ができる人の特徴」と「できない人が陥りやすい原因」、
そして今日からできる具体的な対策を紹介していきます。
「好き」はスタート、「続けられる理由」はエンジン
心理学では、人の行動を動かす力を「動機づけ(モチベーション)」と呼びます。
この動機には2種類あります。
- 内発的動機づけ(=自分の興味・好奇心から学ぶ)
→ 例:「英語が好きだから勉強する」「歴史を知るのが楽しい」 - 外発的動機づけ(=報酬や目的のために学ぶ)
→ 例:「資格を取って仕事に活かしたい」「親に褒められたい」
実は、どちらの動機でも「学びの成果」は出せます。
ただし、長期的に続くのは**“どちらか一方ではなく、両方がうまく混ざっている状態”**だと言われています(デシ&ライアンの自己決定理論)。
つまり、「好きだからやる」と「目的があるからやる」、
この2つのバランスが取れている人ほど勉強を継続しやすいのです。
脳科学から見ても「好き」より「継続」が勝つ
脳の仕組みから見ると、勉強が得意な人ほど「習慣化」が上手です。
最初のうちは「やる気(ドーパミン)」で動きますが、
続けているうちに脳がそれを“日常のルーティン”として処理するようになります。
これは「基底核(きていかく)」という脳の部分が関係しており、
好き・嫌いに関係なく、**“やるのが当たり前”**になることで努力が減るんです。
つまり、「やる気」よりも「習慣」が強い。
これは心理学でも言われている有名な理論です(行動科学の観点より)。

「続ける理由」を見つける3つのステップ
自分が勉強する目的を言葉にする
→ 「合格したい」「自信をつけたい」「人の役に立ちたい」など。
結果よりも“成長の過程”を楽しむ
→ 「昨日より覚えられた」「今日は1ページ進んだ」など、
小さな進歩を見える化すると達成感が続きます。
人と比べず、“自分のペース”で続ける
→ 発達障害や境界知能の人は、理解スピードが他人と違うだけ。
「時間がかかる=劣っている」ではありません。
発達特性があっても勉強したい人におすすめの家庭教師
発達特性があっても、勉強をあきらめる必要はありません🍃
実は、「自分に合った勉強法」を見つけるサポートもあります。
家庭教師ファーストは、私が大学生の頃、勉強に悩んでいた時に、実際に利用した家庭教師サービスです。
オンラインで受けられて、移動の手間もないし、先生との相性を入会前に確認できる無料体験も安心でした。
料金も月ごとなので、学びたいときにだけ利用することも可能でした。
まとめ:「好き」よりも「やめない理由」を持つこと
勉強を続けられる人は、
「好きだからやる人」だけではなく、
**「やめない理由を見つけた人」**です。
好きという気持ちは、最初の火をつけるライター。
でも、その火を灯し続けるのは、目的・習慣・支えてくれる環境です。
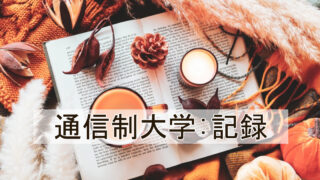





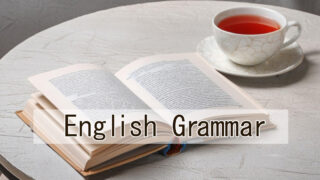


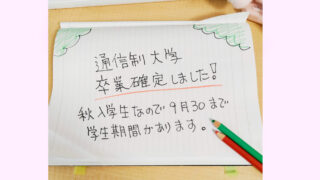

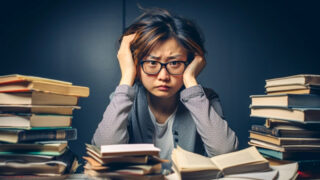


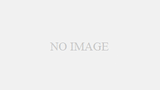

コメント