私は、ASD(自閉スペクトラム症)・HSP(繊細気質)・境界知能(IQ70〜85)という特性を持っています。
勉強そのものは好きでしたが、人との関わりや集団生活がどうしても苦手で、どこに行っても周囲に気を使いすぎて疲れ切ってしまう。そんな日々を長く過ごしてきました。
けれど私は、通信制大学を選んだことで、卒業まで辿り着くことができたのです。これは単なる偶然ではなく、「自分の特性に合った環境を選んだ結果」だと断言できます。
この記事では、なぜASD・HSP・境界知能の私に通信制大学が合っていたのか、そして同じような特性を持つ方にも本気でおすすめできる理由を具体的にお話しします。
なぜ通信制大学がおすすめなのか?3つの決定的な理由
人間関係のストレスが激減する
HSPやASDの方は、ちょっとした会話のトーンや空気の変化にも敏感で、それが大きなストレスになります。私も、10年来の友人と話していても「私、何か変なこと言った?」と不安になり、何も手につかなくなることが何度もありました。
でも通信制大学は基本的に自宅学習。
誰かと無理に会話する必要も、グループワークに参加する必要もありません。
人間関係からくる疲れがないだけで、勉強への集中力が何倍にも上がりました。
自分のペースで学べるから理解しやすい
境界知能の私は、理解に人より時間がかかります。
でも、通信制なら同じ教材を何度も読み返せるし、分からない部分があればネットで検索して調べながら進めることができます。これは、教室で授業を受けるスタイルではなかなかできません。
焦らず、自分のペースで確実に理解できる環境が、私にとって何よりありがたかったです。
ASDの“コツコツ型”が活かせる環境がある
ASDには「一人でコツコツ続ける」ことが得意な特性があります。
通信制大学の学習スタイルは、この特性と非常に相性がいいです。毎日、決まった時間に勉強を進めるだけで、自然と課題が終わり、レポートが完成し、単位が取れていきました。
私にとっては、大学に通うよりも一人で継続できる自宅学習のほうが安心ができて、何倍も効果的でした。

と言う、3つの理由から通信制大学をおすすめします!
私が実践した通信制大学での勉強法【タイプ別アプローチ】
通信制大学では「自分の特性に合った勉強スタイルを見つけること」が何より大切です。
私はASDの“過集中タイプ”で、HSPの思考の深さもあり、一般的な「25分で休む」ようなポモドーロ式のやり方は正直合いませんでした。
ここでは、私自身が実践してきた方法と、他の発達特性を持つ方にも役立ちそうなアプローチをタイプ別に紹介します。
私のような「過集中タイプ」の勉強法(ASD・HSP寄り)
スイッチが入ったら一気にやるASDタイプは、一度集中すると、腰や目が痛くなっても区切りがつくまで止まれません。実際に私もASDのため、ご飯とトイレ以外、席を立たずに何時間もレポートを書き続けることもあります。
- “切り替え”が苦手だから、環境も一貫性を重視
- 別の部屋に行くと頭が切り替わってしまい、戻ってくるのが難しいため、勉強環境はできるだけ一定にしています。
- 思考が深まりすぎるので、疑問はとことん調べる
- HSPの特性もあり、ちょっとした疑問をスルーできず、納得するまで検索・調査・熟考を繰り返します。その過程が逆に理解を深め、自信にもつながりました。
🟡 注意点:集中しすぎて体調を崩さないよう、タイマーを使って強制的に小休憩を取る工夫をおすすめします。
私は普段は、レポートを作る、資格試験の勉強をする、仕事をするというときは、あまりタイマーを使わないのだけど、健康のためにタイマーを使っています。
私が使ったタイマーの中で一番使いやすかったのはリンク:🔗【Amazonで見る】ドリテック(dretec) 大画面タイマーです。画面が大きくて、使い方がシンプルで境界知能の私でも使いこなせます!✨
▼集中が続きにくいタイプの勉強法(ADHD傾向の方向け)
一方で、ADHDの傾向がある方には、「集中を短く区切る工夫」や「目に見える進捗管理」が有効なことが多いです。
- ポモドーロ・テクニックを使う
- 25分集中+5分休憩のサイクルで進める方法。集中しすぎることなく、疲れを予防できます。
- ToDoリストでやることを明確にする
- 「今何をやるべきか」を視覚化しておくと、注意がそれにくくなります。
- ご褒美を設定してモチベーションUP
- 勉強が終わったら好きな動画を見る、甘いものを食べるなど、報酬型学習を取り入れるとやる気が続きやすいです。
- スマホや通知を遮断する工夫
- 気が散りやすい人は、アプリブロッカーや通知オフ機能を活用して環境から整えるのが効果的です。。
勉強法は「自分専用」が正解
通信制大学の最大の魅力は、誰かのやり方に合わせなくていいこと。
ASD、HSP、ADHDなど、発達特性は一人ひとり違います。大事なのは、「世の中で推されている方法」ではなく、あなたに合う方法を見つけて使うことです。
私のように、とことん深く考えて、ひたすら集中して突き進むタイプもいれば、少しずつ、短時間集中でコツコツやるのが向いているタイプもいます。
どちらが正解ではなく、どちらも正解なんです。

大学卒業は誰にでも可能!
特性を持つ方でも、環境さえ整えば通信制大学で卒業できます。私の経験から言うと、特性のある人ほど、自分に合った学び方を見つけることが重要です。「人と同じペースで学べないから無理」と思う必要はありません。
通信制大学は、集団に振り回されず、自分の強みを活かして学べる環境です。あなたも、外部刺激に惑わされずに勉強できる場所を選べば、卒業のチャンスは十分あります。

大丈夫、あなたも卒業できるよ✨
ハンデがあっても、あきらめずに進めば大学卒業も夢ではありません。私も途中で大変だと思う事があったけど、1つずつゆっくり自分のペースで頑張ったら卒業出来ました。
まとめ:諦めないで挑戦してほしい

もし、対人関係や集団生活で悩んでいるなら、通信制大学で学ぶことを考えてみてください。「自分には無理かも」と思う必要はありません。環境を変え、自分に合った方法で学べば、卒業できます!
私のように、HSP・境界知能・ASDの特性を持っていても、通信制大学なら卒業できました。あなたにも、同じチャンスがあります。勇気を持って一歩踏み出してみてください。



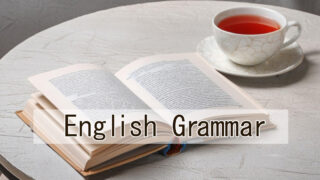
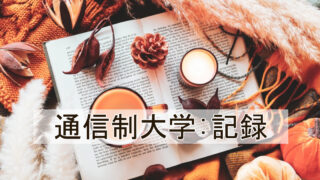




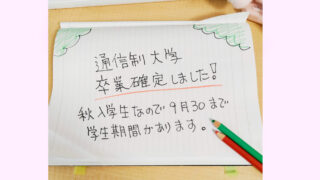




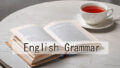
コメント